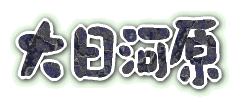|
ホントに姫路藩、
血なまぐさいことはとりあえず、
市川でやろうとしてますね!
ここ大日河原も、処刑やら砲撃やら、
一般市民が近寄りがたいイベントが目白押し。
演習ともなれば、
河原から向かいの高木山まで(距離約760m)、
盛大にぶっ放してました。
って・・・高木村・・・
人が住んでたハズなんですが。
士農工商の時代にゃ、関係ないんですかね。
|
 |
他にも、野里の日吉神社から、
伊伝居山までぶっ放した記録も。
無人戦闘機を飛ばすような軍隊でも、
誤射するのに、お前らホントに大丈夫なのか?
残念ながら、記録が残ってないので、
どんだけ農民の頭上に降り注いだかは、
解りませんけどね。
たちの悪さは北の某国並ですよ。
と、地図上では大日グラウンドがあるはず・・・ |
 |
って、見事な桜並木がお目見えですか!
312号から土手で隠れたこのグラウンド。
意外に発見しにくいのか、
花見客もほとんどいない。
何せ、軍隊が人家に向けて、
大砲撃ってた現場ですからね。
あまり大っぴらになってるハズがないんですよ。
|
 |
でも、ちょっと回り道をすりゃ、
車でもたどり着けます。
姫路の桜スポットは、
車じゃ行きにくいトコが多いので、
中々、ポイント高し。
ところで姫路藩、300年の安寧な日々に、
頭のネジが緩みきったのか、
演習でアホなことを思いつきます。
|
 |
「熟達者には、
砲弾の重量を名前に冠することを許す」
つまり、
「俺はこんだけの威力の弾を撃てるぜ」
と自慢させたワケですね。
つまり、
・・・・兵器が自分で、
性能を明けらかしたワケですね!
戦いの世界では、
自身の性能を誇張はすれど、
明確にはしないのが普通。
何せ、性能がバレバレだったら、
相手はそれを考慮して戦術を練れば、
事実上、その兵器を無効化できるんですから。
「俺の弾はここまでしか届かないぜ!」
と、高らかに宣言してるようなもんですよ。
|
 |
野口二貫左衛門ってな具合に。
・・・でも二貫って、
意外に頑張ってます。
何せ約7kgの弾をぶっ放すわけですから。
しかも、姫路藩で最も多く、
二貫の名前を戴いている流派は、
関流で、膝上砲射を専門にしていたとか。
膝の上で大砲をぶっ放す!?
どうやってやってたか、
資料が手元にないんで想像もつきませんけど、
戦後は大道芸で食っていけますよ!
一回でいいから、見てみたい。
←話が逸れますけど、この桜並木、
シンプルに見事です。
荒んだ話ばっかりな世の中で、
心が洗われそうですゼ。 |
 |
グラウンドではどっか陸上部が練習中。
この桜の中でとは贅沢ですな。
そういえば穴居人は知りませんでしたけど、
砲術にも流派があったらしいですね。
姫路藩には、
荻野流、関流、不易流、
高島流、佐々木流、自得流、井上流
の7流が伝わっていたらしい。
鉄砲ぶっ放すのに、
流派があるだけでも驚きですけど、
幕末の動乱も近い時代に、
西洋式砲術を採用していたのが、
高島流だけとは・・・・
後の連中は戦国時代仕様ですか? |
 |
土手越しには、対岸の桜も映える、
こんな景色も。
入学式の日に、わざわざこんなトコを歩かせて、
ムービーをとりまくるのもオツかも知れません。
ちなみに300年間、
一度も大砲を使うことのなかった姫路藩。
しかしついに戦いの時がやってきました。
時は幕末。
長州征伐です。
まあ、大将がトンズラこいたので、
岡山から逃げ帰っただけなんですが。
結局、300年磨きに磨いた腕を、
披露する機会はないのか・・・
|
 |
否!
まだ篭城戦がありますぜ!
姫路藩といえば、当時バリバリの佐幕派。
何せ将軍の逃避行に、
姫路藩主がちゃっかり同行しちゃってますからね。
それぐらい、幕府の重鎮。
しかも西国最前線!
もう京都で一戦交えて、
負けちゃってる後なんで、
最前線なんかは微妙ですが、
まだ戦えます!
薩長連合軍をここで食い止めるのだ!
余談ですけど、←ココ、菜の花もキレイです。
|
 |
なのに、あっさり開城しちゃいました。
しかも、700m圏内(男山と景福寺山から)という
まるでこの演習場を見越したかのような
距離からの射撃を受けての開城。
さぞや屈辱的でしょう。
「撃ちてぇんだよ。
俺の方がもっと上手く当てれんだよ!」
とまあ、一武士がのたまわったのかも知れませんが、
時代の流れについていけず、
結局一度も役に立たないまま、
終戦を迎えるハメに。
←ココが対岸、大日河原の桜といえば、
コッチの方がなじみがあるかも。
|
 |
何より、可哀想なのは、
近代戦に投入される新式の大砲に、
彼らのテクが通用しなかったことですよ。
まあ、近代兵器は膝では打てんです。
というわけで、
大砲の流派はもうほとんど現存してません。
残ってたら、
祭りの時とか引っ張りだこなんやろうに・・・。
残念でたまりませんよ。
まあ、300年練習して、
曲芸扱いじゃ、
それこそ屈辱的なのかも知れませんが。
最後は312号から。
コチラは見慣れた方も多いはず。
今度は是非、
この裏側にも足を運んでやってくださいな。
|